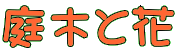
庭先で咲いた花や、植木の手入れなど紹介します。
2025年5月11日
春の庭木の剪定
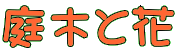
庭先で咲いた花や、植木の手入れなど紹介します。
2025年5月11日
春の庭木の剪定
2024年11月3日(日)
秋の庭木の剪定、手入れ 無事終了!
| 我が家の年中行事の一つ、秋の庭木の剪定を無事に終えた。11月で81歳になった。おかげさまで元気に過ごしている。この歳で「脚立に登り剪定をするのは危険だ!」と思いながら、落ちないよう注意し作業を行った。 マキは電動バリカンを買ったので、あっという間に終わった。最後の仕上げを刈込ばさみで丁寧に行う。 マキは低木なので、立ち仕事でできる。ただ、切った葉が飛び散るので、ブルーシートを敷き、丁寧に養生し、後片付けの手間を省くようにした。これで葉っぱが飛び散らず楽に収集できた。 松は門担ぎの枝を昨年切り詰めて短くしたので作業量が減った。今年はさらにこの枝を思い切って幹から切断した。 “この枝を切るかどうか”は相当悩んだ。 判断するため、写真を撮り、画像処理でこの枝を消して見た。庭の内・外側の姿をプリントして画像で見比べ検討し、切断を決心した。 門担ぎの枝は15cmほどの太さに成長していたのでノコギリで切るのがしんどかったが、何とか切ることができた。 剪定に取り掛かる前に切り離したので、剪定作業は3割ほど減ったので楽ちんになった。 その結果、枝が無くなり、スッキリしたように見える。やって良かった!! 今年の秋は暖かな日が続いていたので切った幹から松脂が噴き出してくる。そのままでは、この松脂が落ちて周辺がベタベタになり大変なことになる。そこで、包装用伸縮テープでグルグル巻きし、松脂が落ちないように処置している。 マキ、松、台杉の剪定で、46L入りのゴミ袋の6袋になった。木が大きくなると葉っぱの量も半端でなくなる。 剪定作業の前後、BeforeとAfterの写真をご覧ください。 剪定前(Before)  剪定前;松の門担ぎ(枝)を切断後;門の外からの眺め  剪定前;玄関からの眺め;ぼうぼうに葉が茂った松とマキ  剪定後;玄関からの眺め;スッキリとした松とマキ  剪定後(作業終了後);門の外からの眺め;台杉も高さを低くして、剪定済み  ゴミ袋3袋 他に3袋のマキ、台杉の葉があった。  年齢と共に、身の回りをダウンサイジングしつつある。枝の切断もその一環。 今年もこれで年末、お正月を迎えられる。 |
2023年11月3日(金)
松と槇と台杉の剪定 ダウンサイジング 無事終了!
| 毎年、11月3日の文化の日前後に、庭のマツ、マキ、台杉の剪定をするのが、年中行事になっている。 しかし、11月は誕生月で、誕生日が来ると満80歳という節目になる。何とかこの歳まで生き延びてきた。 おかげさまで病気をしながらも、元気に過ごしているので、今年も剪定作業を2日間かけて行なった。 その剪定作業の経緯を紹介する。 剪定前の姿 マツ、台スギの葉が伸び放題で、、うっとうしい姿になっている。半年経てばこの状態になる。 今回は、思い切って、松と杉のダウンサイジングを試みる!  庭のマキの葉も伸びてボサボサの状態(作業前)  まず、マキから剪定開始。手前にマキタの電動バリカンが見える。 今回は、刃先を新品に交換したので、抜群の切れ味だった。  奇麗にカットされ、見事なマキの姿に変わった。  いよいよ、本番! 松の剪定開始! 大きな3本足脚立に乗って、最上部の枝の葉をむしる! 脚立は落下防止のため、大きなものを使っている。運ぶのが大変だが、安全第一!  台杉は3本を2本にした  作業終了、完成した姿 スッキリ、明るくなった感じです。  年中行事とは言え、加齢とともに高所作業が怖くなる。足が思うように素早く動かない。 未だ、踏ん張りが効くので、何とか作業ができる。 今回は、今後、楽に作業できるように、相当、木の枝を切り、縮めてみた。それでも、剪定した葉の量がビニール袋に6袋になった。史のゴミ回収日だったので、直ぐ回収してもらい、すっきり作業は終了した。 安全に終わってホッとしている。これで、正月が迎えられる!! |
2020年11月1日(日)
松と槙と台杉の剪定
| 今年も秋の剪定の季節になりました。最低気温が10度前後になると、木々の樹液が流れなくなり、木が冬ごもりに入ります。そして葉が枯れたり、紅葉したり、落葉したり季節の移り変わりを感じます。 特に、松は枝を切ると、松脂(マツヤニ)の樹液が垂れだして、周囲を汚しますが、気温が下がれば、樹液の吹き出しが少なくなります。 この頃に毎年庭木の剪定をしてきました。今年もそのシーズンになりましたので、老齢に鞭を打って、今年も取り組みました。今までは、ハシゴに乗って作業するのは疲れを感じなかったのですが、この数年、少々体力的な負担を感じます。 さて、手始めに槙から剪定を始めました。槙の剪定は、刈り込みばさみで刈れば済みます。最近はバリカン式電動刈り込み機が販売されていますが、我が家は相変わらずハサミを使って、手でやっています。 まずは、剪定前の槙(マキ)の茂った状態です。半年間でこれほど葉が伸びるので、樹勢は元気な証拠です。 槙の剪定   Before After 松の剪定  Before  After 今年の剪定の狙いは、『Down sizing すること!』(切り詰めて、小さくすること) 木は年々、成長し背丈も高くなり狭い庭に占める嵩が増えてきます。うっとおしくなります。 さらに、剪定の際の手間暇がかさんできます。 そこで、思い切って、枝をすかしたり、短く切断したりしました。 松、マキ、台杉の姿もこれですっきりしました。 剪定した葉や枝の量は、40リッターのゴミ袋に3袋分になりました。市の一般ゴミとして処理します。 |
2019年11月6日(水)
松と槙の剪定
| 秋の気配になり、近くの星田妙見宮の参道に生えているイチョウが黄色に色づき、 ギンナンの実が落ちています。それを近くの人が拾いビニール袋にたくさんの実が入っていました。 毎年、文化の日の前後に、庭の植木の手入れを欠かさずやってきました。今年は思いもよらない病を患い、夏から入院・手術とあわただしい日々を過ごしました。庭の手入れができるかな?と気がかりでしたが、お陰様で今年も、少々手抜きは免れませんが、やり終えました。   例年はBefore&Afterとして、選定前の写真も添えていましたが、今年はBeforeの写真を撮り忘れましたので、選定後の姿しかありません。 この木々は植樹後30年が経ち、次第に庭木としての貫禄が出てきました。幹は随分太くなり、その分、枝が伸び、葉が茂りという状態になり、剪定すると、枝と葉っぱで大きなビニール袋(40L)に、松だけで5袋、槙は1袋もありました。 そこで、槙は初めて枝を2本切りました。昨年の写真と見比べれば分かりますが、枝を切ってすっきりとした樹形になり、切ってよかったと思っています。松も同じく枝を切ったり、縮めたりして、選定が楽になるようにしましたが、こちらも縮めて良かったと思います。 30年も自分で剪定をしてきますと、次第に要領が分かってきます。 交野市のシルバーさんが近所の庭の手入れをしていますが、松などは当初の姿から想像がつかないようなみすぼらしい姿や樹形に代わってしまっています。 我が家の松と台杉と槙は自分で今までやってきましたので、自己流ですが樹形は整っていると自負しています。 |
2018年11月3日(土)
松と槇の剪定と、蹲(つくばい)の手入れ
| 毎年、文化の日の前後の小春日和に、秋の庭木の剪定を行ってきました。庭木は松と槇(まき)の2本です。 この両木は毎年2回の剪定をしてきました。 自宅は平成1年に建直したので、かれこれ30年になります。自分ながら『よくぞこれまでやって来たな!』という思いです。松は植えた時は、ひょろひょろとしたみすぼらしいものでしたが、今は年輪を重ね、随分しっかりした「門担ぎ」となりました。同様に槇も太くなり、幹には苔が生すほどになっています。 自分の歳が11月で後期高齢者の仲間入りし、体力の衰えを次第に自覚するようになりました。この歳で、脚立に登って松の剪定をするのは、足元がおぼつかないので、3本脚の剪定用脚立の一番大きなものを買って保管しています。この大きさなら、脚立の一番上に載らなくても十分手が届きますので、落下することはまずありません。 剪定は年2回行います。初夏に松の新芽(松ロウソク)が伸びて、しばらくしてからローソクを切るのですが、同時に樹形を整える作業をします。 松は秋口まで葉が伸びますので、正月を迎えるまでに樹形を整える剪定をします。 槇は松に合わせて、刈り込みばさみと剪定ばさみで行います。槇は葉をはさみでカットする作業ですから、これは誰でもできます。最近は電動刈り込みばさみが売られていますので、これを使えば、30分ほどで終わりますが、年2回の剪定に買うのはもったいないので、相変わらず刈り込みはさみ(手動)でやっています。 槇の葉が散らばらないように、ブルーシートで周囲を養生してから剪定します。これを怠ると、葉が一面に散らばりますので、後作業が大変です。  松の剪定は難しいと言われていますが、30年もやっていると自分流の剪定ができるようになりました。 松の剪定は難しいと言われていますが、30年もやっていると自分流の剪定ができるようになりました。この流儀が正しいかどうか分かりませんが、30年経っても樹形はきちっと保てています。 剪定の前に、はさみ類の刃を砥石で砥きます。この砥をしないと、切れ味が悪く難儀します。槇の剪定から始めましたが、途中で不注意で、砥いで切れ味の良い刈り込みばさみの刃先を右手の親指にちょっと当ててしまいました。 約1cmほど切傷を負い、これはまずいなと思いながら、傷ばんそうこうを貼り、血がにじんだ親指を気にしながら作業を進めました。2日の昼過ぎのことです。 何とか、槇の剪定を終了しました。  さて、3日は天気の特異日の文化の日です。  毎年、この頃に剪定をやるのですが、例年なら2日間かかりました。 毎年、この頃に剪定をやるのですが、例年なら2日間かかりました。今年は全日、親指を怪我しましたので、左手にゴム手袋、右手に超薄手のゴム手袋をはめて、松の葉を引きちぎる作業を始めました。松はクロマツですので、葉が固く、葉の先が手の甲に当たると、針で刺されたような痛さと、赤い点々が生じます。これが風呂に入ると、ヒリヒリと痛くて、『ほろし』が一面に出たような姿になります。  松の剪定は、大変だなあと思ってやってきましたが、今年は手袋のおかげで、作業が例年より4倍も速くできました。毎年2日かかっていたのが、何と3日の午前中で終了しました。 松と槇の剪定した葉っぱの量は、45リットル入りごみ袋で5袋もありました。 火曜日の一般ごみに出します。 松の右側にもう一本、ダイスギがありますが、これは剪定の内に入らず、枯れた枝の取り除きと、伸びた枝や葉をハサミで処理すれば終わりです。  さらに、蹲周辺の清掃、手入れをしました。 さらに、蹲周辺の清掃、手入れをしました。小砂利の色が青っぽいものしか手に入らなかったので、仕方なく敷きましたが、今までの小砂利と明らかに色の違いが分かります。 蹲(石臼のような形)の周辺に敷き詰めている中粒砂利の配水管が詰まったので、砂利を全部取り出した後、配水管を掃除して、周囲から土が流れ込まないようにセメントで目づめしました。 これですべて終了です。 正月を迎える準備は出来ました。 いつまでこの作業ができるかな? 楽しみながらやれるところまで、やろう!! |
2018年4月21日(土)
松のローソクの剪定 Before & After
| 今年は桜の開花が例年より2週間ほど早く、3月下旬に咲きました。季節の移り変わりが地球温暖化現象の影響かどうか分かりませんが、早く暑くなっているようです。今日は交野市でも27度ほどありました。全国の気象予報では30℃を超えたところもあるようです。4月下旬でこの暑さですから、真夏にはどうなるか?今から心配です。さて、我が家の松もこの異常気象で、ロウソク(新芽)が大きく伸びています。 昨年は4月27日に剪定していますが、今年は約1週間早く今日作業をしました。 いつものとおり、作業の前後の写真を撮りましたので、UPします。 例年と同じようなことを繰り返していますが、今年は思い切って枝を抄かせましたので、作業量は大分減りました。さらにもう少し枝を切り詰めて楽に作業ができるようにしたいと思います。まずはこの樹形で夏を越させます。  ロウソク(新芽)がバケツに2杯ありました。 この剪定は、指で摘まんで折るという作業です。 枯葉や込み入っている枝もついでに剪定しました。 樹形は相変わらず保てています。  |
2017年11月4日(土)
秋の庭木の剪定をしました
昨年も同じ頃に、庭木の松、槇、杉の剪定をしました。今年も秋季近畿高校野球
大会のNHKラジオ放送をポケットラジオで聞きながら、小春日和の暖かい晴天の
下で庭木の手入れ、剪定を行いました。昨年は思い切って枝を縮めましたが、最近
松と槇は大きく根を張ってきましたので、樹勢はますます盛んで、枝や葉を半年で
ぼうぼうに茂らせて伸び過ぎてしまいます。今年は槇の剪定時に、ブルーシートを
張って、葉っぱの後始末を短時間で終われるように、ていねいに養生をしました。
昨年同様に大量の枝や葉っぱをごみ袋に詰めて、市のごみ回収に出しました。
写真は、剪定前後のBefore&Afterです。殆ど昨年と変わりがないと思います。
我流の剪定、庭師も30年近くやりますと、プロの庭師の領域に近づきました。
言い過ぎかな?

⇓


⇓

2016年11月26日(土)
秋の庭木の剪定をしました
恒例の年中行事の庭の松と槇と杉の剪定をしました。昨年は11月8日にアップ
しましたが、今年は少し遅れました。松は次第に大きくなり、剪定が大変労力が
いるようになりましたので、今年は枝を思い切って切ったり、縮めたりしました。
それでも、90リッター用ごみ袋に5袋ありました。例年同様に剪定の前後の姿を
写真に撮ってBefore & Afterとして掲載します。
槇の剪定の前後の姿

⇓

松の剪定の前後の姿

⇓

庭の草花


千両と万両の赤い実がとてもきれいです。
近年、庭や野菜畑に皇帝ダリアがきれいに咲いています。
霜が降りるとあっという間に花が萎れます。高さは2m以上。
竹のような節のある木に薄いピンクの可憐な花が咲きます

では次回をお楽しみに! ご覧頂きありがとうございます。
![]()
2015年11月8日(日)
秋の庭木の剪定をしました
毎年11月に狭い庭に植えている松と槇と杉の剪定をするのが、恒例になって
います。この時期は気温が下がって作業が楽にできること、晴れの日が多い
ので、屋外の作業が気持ちよくできるからです。もう一つの理由は、松の木は
枝や葉をむしりますと松脂(マツヤニ)が噴出してきます。これは気温が高いと
大量に出ます。この時期になりますと、手や剪定ばさみの刃に少し着きますが
マニキュアをはがす液で拭けば、うまく取れます。そういう訳で今年も文化の日
をめどに作業をしました。松の木は年々大きくなり、幹は根元で直径が20cm
余りになりました。と言うことは、むしった葉っぱの量も増えて、90リッター用ゴミ
袋に3袋と半分ありました。これだけ葉をむしると、指先が痙攣するほどです。
槇と、大杉は刈込バサミと剪定バサミで、ザクザクとやれば終了ですので、
こちらは楽です。 今年の剪定前後の姿も例年どおり、写真に収めました。
Before & After として掲載します。
昨年度の写真と比べて、全く同じような姿に映っていますが、これは庭師さん?
の腕がいい証拠でしょう! 自画自賛です。 この作業を27年続けてきました。
では下の写真をご覧ください。
Before 生い茂った松

Before 葉が伸びた槇(マキ)

After すっきり整った松

After 坊主頭になった槇

では次回をお楽しみに!!
ご覧頂きましてありがとうございます。
![]()
2014年11月23日(日)
秋の庭木の剪定を終えました
| 今年は勤労感謝の日が日曜日だったので、3連休の人が多かった事と思う。 ただ今、秋の行楽シーズン真最中で、紅葉がとても綺麗な時期で、裏山の大阪府民の森の吊り橋『星のブランコ』もたくさんの人で賑わっている。 天気も大変良く、まさに『小春日和』、気温が18度ぐらいで、風もなく日だまりでは、ほっこりと暖かい。 例年は11月初旬、文化の日の前後に秋の庭木の剪定をするが、今年は都合で少し遅れた。 マキは11日にやっていたので、昨日と今日の2日で、松と杉を剪定した。 この前は、下の『松のロウソクの剪定』にもあるように4月27日に春の剪定をやった。それから半年余りになる。庭には松と槇と杉が植わっている。 これらの木は、平成元年に家を建てた際に植えたので、早くも25年経ち、木が大きく太くなってきた。 剪定の際に出る葉っぱや枝の量が半端ではない。大きなゴミ出し用の袋に4袋にもなる。松の木の天辺の枝を切り、葉をむしるには背丈が伸びてきたので、植木屋用の3本足の脚立を買い、普通の脚立2個と併用して使っている。 『剪定していて落ちて怪我をした』という話を聞くので、そういう失敗がないように道具だけはしっかりした物を使っている。 秋の剪定は、夏場に葉や枝が茂るので、剪定には時間がかかる。特に松の木の針のような葉は手に刺さり、チクチク痛いがそれを気にするとこの仕事はできない。松は松脂(マツヤニ)がすごく出るので、服や手に着くとなかなか取れにくい。マニキュアの『リムーバー』液を買って、これで手を拭き取っている。 2日間の剪定作業も、年齢的にそろそろしんどくなってきた感じがする。いつまで出来るか? まあ、楽しみながらやれる内はやろうと思っている。 剪定のBefore & After の写真をアップしますのでご覧ください。 マキの剪定の前後  Before Before After Afterマツと杉の剪定前後  Before Before After After Before Before Afte Afte |
4月27日(日)
松のろうそくの剪定
この季節に、松の新芽(ろうそく)がドンドン伸びます。
この芽を摘んでおかないと、樹形が崩れてしまいます。
4月23日(水)
庭の紅白のボタンが大きな花をつけました
今年も大きな花がつきました。白のボタンは庭先に直植え、
赤いボタンは鉢植え。
白い花は、3個切り花にしたので、全部で6個咲きました。
玄関に入ると、何とも言えぬ香りが漂っています。
1月10日(金)
我が家の庭の蝋梅が咲いています
| この寒い季節に花を咲かせる蝋梅が香りを放って、今年も咲き始めました。 蝋梅とはよく言ったもので、その花弁はまさに蝋細工のようで、薄い黄色で 透きとおるような薄い花弁です。梅の木より一足早く咲くことで、この質素な 花に目を引かれます。 けなげな花、蝋梅。 ショットを2枚アップします。   |
11月24日(日)
庭木の剪定
| 我が家の年中行事?となっている庭木の剪定をしました。松とマキの2本が 庭に植わっています。この庭木は家を建てた平成元年に植えたもので、25年になります。 植えた時は、木が若くて頼りないものでしたが、歳月が過ぎ、最近はその存在感を増してきました。というのも、この25年間、初夏と年末の年2回、欠かさず自分で剪定作業して来ましたが、この数年、剪定した時に出る葉っぱの量が多くなりました。 今年も2回目になる初冬の剪定を3日間かけて行いました。ごみ出し用の大型のビニール袋にちぎった松の葉、マキの葉を入れて市のごみ収集の際に出すのですが、今回はマキの葉が2袋、松の葉が5袋になりました。大変作業量が増えました。それだけ木が大きくなったのです。 自分もいい年齢(70歳)になりましたので、この作業をいつまでできるか、少々気にかかるようになりました。 と言いますのも、作業後、腕のだるさや筋肉痛、脚立に乗りながら腰を曲げて松の葉をちぎる高所作業は腰に負担がかかりますので、腰痛もあり、パテックスを張って何とか、作業を済ませました。 松の軸の太さや、軸の皮の荒々しさが樹齢と共に古びたいい感じになってきました。今年は思い切って小枝や枝先を切り詰めたのですが、葉が太くなり、硬くなってきましたので、手に刺さってチクチクします。 松の木は、手入れをしっかりすれば素晴らしい樹形を楽しませてくれますが、手を抜けば、ぼうぼうになって見る影もなくなってしまいます。 『何事もきちんと手入れをする』ことが肝心だと思い知らされています。 昨年は12月4日に剪定して、このページの下の方にアップしましたが、それと見比べて頂くこともできます。 樹形を維持することが結構難しいのが松の剪定です。素人がやれば、数年で樹形が崩れてしまいます。これで25年間、自前でやってきましたが、だんだんと樹形が整ってきたなァ!と自画自賛しています。 まあこれで、新しい年を迎える準備が一つできました。 剪定のBefore & After をアップしますので、ご覧ください。
 松だけでこんなに大量の葉をちぎった。袋は70リッター入りのもの5袋。 |
| 猛烈な夏の暑さも和らぎ、朝夕は随分静しくなってきました。 昔の人はよく言ったもので、『暑さ、寒さも彼岸まで』のとおり、この6日間は昼間は真夏日(30度超)ですが、朝はひやーとした空気を感じます。 それにしても、自然界は素晴らしいなと思います。秋のこの季節になると、必ず田んぼのあぜ道に赤い彼岸花を咲かせます。今年も今沢山咲き誇っています。最近家の庭に、白や黄色やピンク色の彼岸花を見ろことがあります。観賞用として品種改良したものだそうです。白い彼岸花を見つけて写真に撮りましたので、畔の赤色と一緒にアップします。   先日の台風19号の雨で、天の川の堤防の一部が崩れて補修 工事中です。川はまっすぐ流れている場所なので、なぜ崩れたのか? 多分、工事不良が原因でしょう。こんなことで壊れるようでは安心できません。  |
1月13日(日)
庭の蝋梅と千両と万両
 |
| 千両の実 |
 |
| 万両の実 |
 |
| まさに蝋のような蝋梅の花 |
12月4日(火)
庭木の剪定(その2)
| 11月7日に庭木の剪定を始めたことを書いたが、その続きの作業を報告。 松の木は、植樹して約20年以上になり、最近、幹が太くなって本格的な庭の松という感じになってきた。 半年間で葉が茂り、ずいぶん剪定作業量が増えてきた。 特に松の木は、針のような葉なので、手に刺さり、チクチクする。大変な作業である。枝はよほど注意して剪定しないと、一度切断すると、そこからは芽が出ないので、枝振りが代わる。 さらに、一本一本、針のような葉をむしらなければならない。 松は松ヤニが噴き出すので、手にヤニが付きベタベタする。 作業の途中で、一休みする時は毎回、手を石鹸で洗い、その後、ヤニをマニュキュアリムーバーを使って拭き取るようにしている。その後、もう一度、石鹸でよく洗う。こんなことを、休む度に繰り返す。昼食時も同様である。 マキの木は、剪定ばさみと刈込ばさみで、サクサクとやれば終わる。この作業はいたって簡単。木の周囲に葉が散らばらないようにブルーシートを敷いて、養生をしてから作業を開始する。こうすると後始末が早く済む。 松はその点、マキの何倍も手間暇と、技術がいる。このマキと松は植えてから20年余り、自分で剪定をやってきたので、わが子のようなものだ! 自分の思いのままの姿になりつつある。 そんな松の剪定は年に、二回夏と冬、6月と11月に行っている。今年は少し遅れて12月初めまでかかった。 松の背が高くなったので、三脚の剪定用の脚立を買い求め、高所作業も安全にできるように投資した、家には脚立が4つもあり、どんな高さにも対応できるようにしている。 剪定後の姿を写真に撮ったので、アップします。 |
 剪定前の姿 |
 剪定後の姿  散髪した頭のようにすっきりした松の姿 むしった葉が90Lのごみ出し用ビニール袋に3袋もあった。 これで正月が迎えられる。 |
11月7日(水)
庭木の剪定(その1)
| 朝夕の気温が下がり、今日は立冬、暦の上では冬に入った。庭のマキの木が 茂ってボサボサ頭のようになったので剪定をした。 庭木はもう一本、松の木が植わっているので、来週は松の剪定をしようと考えて いる。こちらは相当、性根を入れてやらないといけない。松の葉は丁寧にむしり とる作業になる。針のような葉なので、手に刺さりチクチクする。 その点、マキの木は刈込ハサミでサクサクとやれば終わる。 綺麗になったマキの木と、来週、手を付ける松の木を写真に撮りました。 |
6月16日(土)
胡蝶蘭が咲きました!
沢山の花芽ができていましたが、やっと花を咲かせました。
店で売っている胡蝶蘭の花のイメージではなく、花の枝が
いくつかに分枝して、それに花をつけるという変わった咲き方
になりましたので、すぐに切り花にして花瓶にさしました。
昨年植え変えして、小さめの鉢にミズゴケで植えましたので、
今年はそのままにしようかと思っていたのですが、気が代わり
植え替えをしました。材料は同じミズゴケにしました。
一週間後から、水やりを兼ねて液肥を与えます。ドンドン成長
させる時期です。
写真は、我が家の玄関の花瓶にさした胡蝶蘭です。

![]()
5月6日(日)
冬を越した胡蝶蘭
冬の寒さに極端に弱い胡蝶蘭(コチョウラン)がこの2年
無事に冬を越して芽をつけました。今年の花芽は一株に
二つ出て、それが異常な形に成長している。何が原因か
分からないが、もうしばらくで開花するはず。
気温が上がってきたので、松の木の下の木陰に出した。

![]()
ここからこのページはスタートです。
深紅と純白のボタンが咲きましたが、花の命は短い。
今年の真っ盛りのボタンです。

